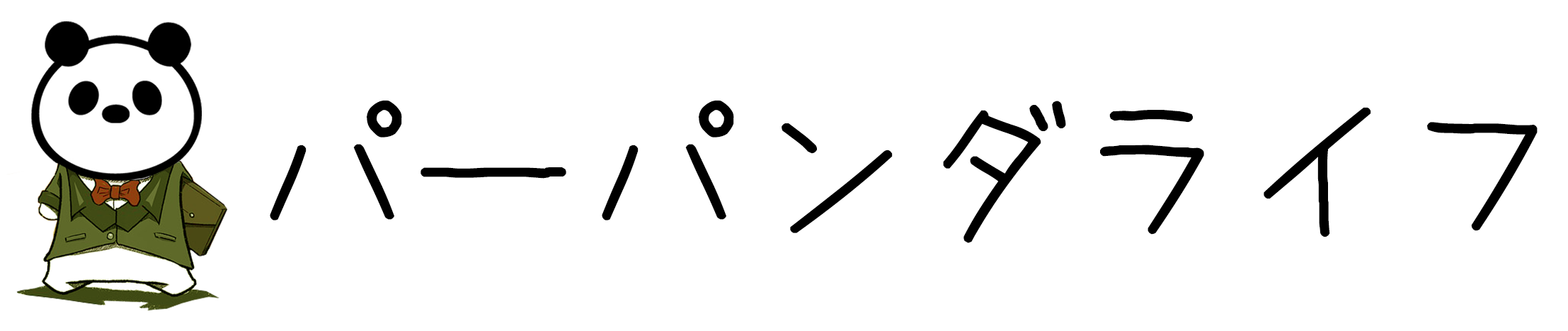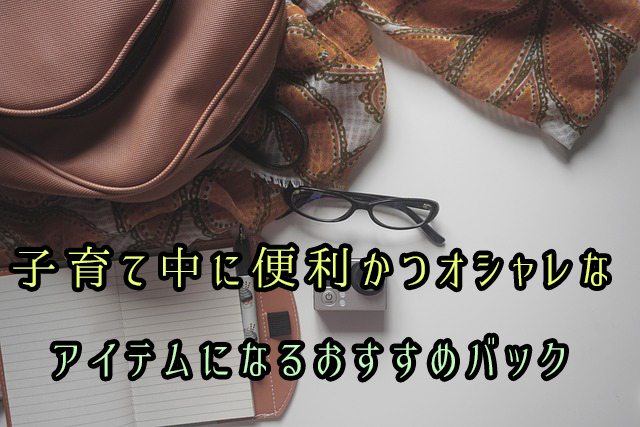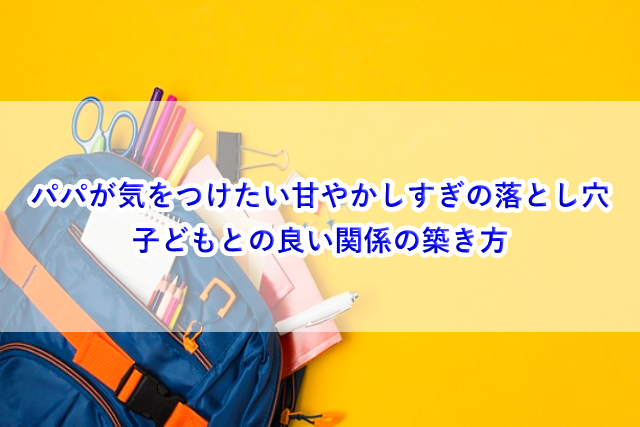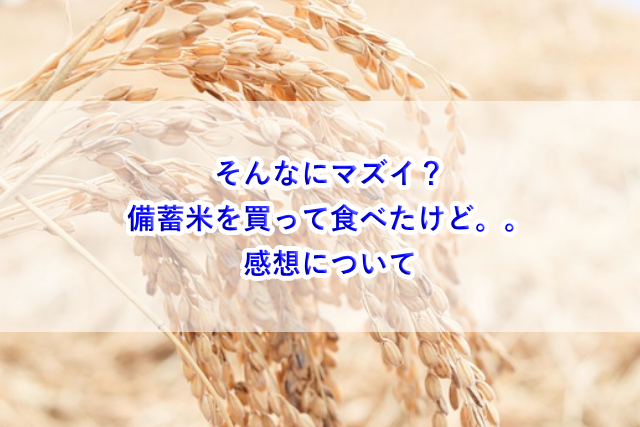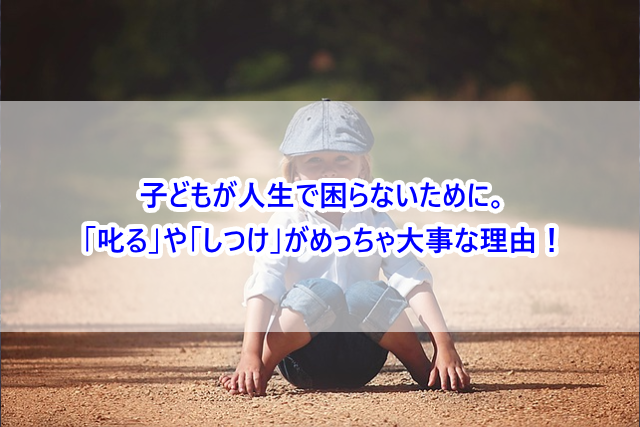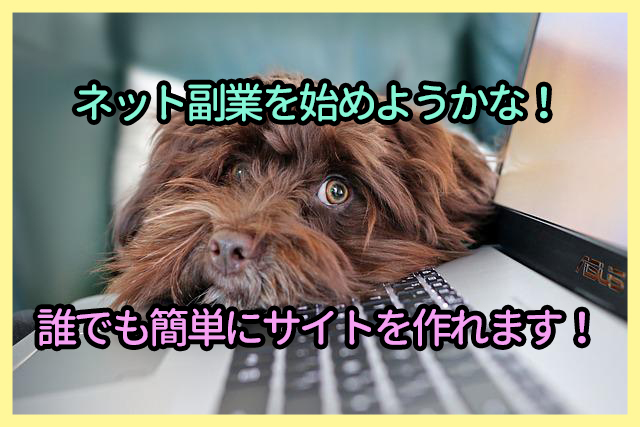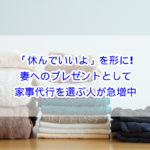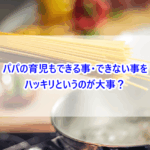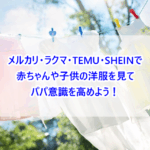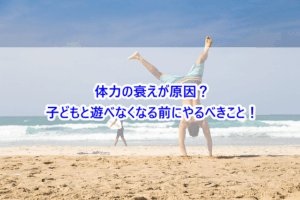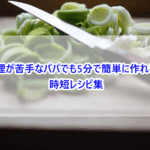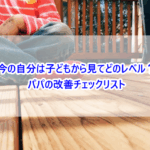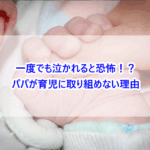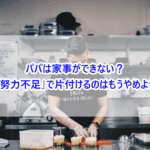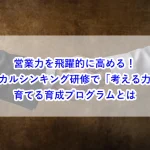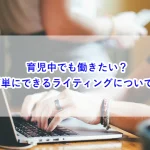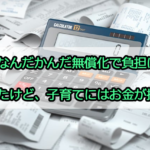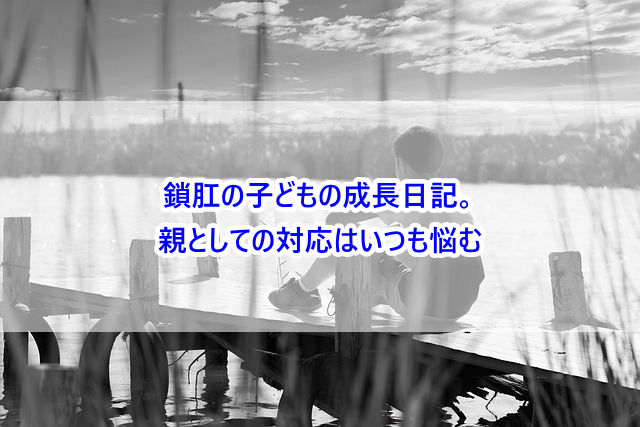
我が子は鎖肛という病気を持って生まれてきました。そして、成長段階で問題・悩みも沢山生まれて都度、対応が必要となっています。
これは、今現在も鎖肛という病気を抱えた子どもと親の成長期となります。
今回は、鎖肛の子どもの成長日記。親としての対応はいつも悩むについて書いてみようかと思います。
最初に困ったこと。戸惑いと不安の毎日
お尻の穴がない――この事実だけで頭の中がパニック。
それでも、看護師さんや病院のサポートのおかげで、少しずつストーマ(人口肛門)やパウチの扱いにも慣れていきました。
ただ、心の中はそう簡単には整理がつきません。
妻は「自分のせいでこんな体に生まれてきた」と自分を責めていたし、
「将来、イジメにあったらどうしよう」なんて不安がずっと頭から離れませんでした。
それでも、夫婦でいっぱい話し合って、医師にもどんどん質問して、
目の前の課題を一つひとつクリアしていくことで、少しずつ前に進んできた気がします。
成長とともに変わる悩み。漏らすたびに感じるもどかしさ
手術が終わって、パウチが外れ、少しずつお尻からの排便が可能に。
でも、ここからがまた大変。
自力で排便ができるようになるまでは、しばらく浣腸が必要。
オムツを卒業してパンツになると、漏らしてしまうことも何度もありました。
「どうしてトイレでしてくれないの?」
「漏らしたらちゃんと教えてよ!」
って、つい口うるさく言ってしまうんですよね……。
でも、本人だって好きで漏らしてるわけじゃない。
肛門の筋肉が弱くて、意図せず出ちゃうこともある。
それが恥ずかしくて言えない――そんなこともあるのかもしれません。
小学生になっても油断できない
小学校に上がっても、まだ時々パンツにうんちがついてしまうことがあって、
「このままだと、クラスでバレたらイジメに繋がるかも……」と不安に。
実際、先生の機転で救われたことも何度かあります。
本人はあまり深く考えてない様子だけど、親としてはハラハラの連続。
声をかけたり、気にかけたり、対策を考えたり……
でも、やっぱり「見守ること」くらいしかできないんですよね。
親としてできること。寄り添い、支えるという選択
子ども自身も少しずつ、「うんちが出そう」って感覚が分かるようになってきました。
だから、最近は漏らす回数も減ってきています。
でも、完全に失敗ゼロになるまでは、もう少し時間がかかりそうです。
親としてできることは、運動を取り入れて肛門周りの筋肉を強くする手助けをしたり、
無理せず、子どものペースに合わせて見守ってあげることくらい。
「変われるもんなら変わってあげたい」――そんな気持ちはずっとあります。
でも、病気は本人のもの。
だからこそ、親は“支える”というポジションをしっかり保つしかないと思うんです。
ちなみに、僕自身もアトピー性皮膚炎を小さいころからずっと抱えてきたので、
「本人にしか分からない痛みやツラさ」はよくわかります。
だからこそ、息子にも「一人じゃないよ」ってことだけは、ちゃんと伝えたい。
まとめ
鎖肛という病気を持って生まれてきた子どもとの生活は、正直、大変なことも多いです。
でも、それ以上に「一緒に乗り越えていこう」と思える瞬間もたくさんあります。
● ストーマ生活に慣れるのも最初は不安だらけ
● 手術後も、排便のことで悩みは続く
● 小学校ではイジメのリスクにも直面するかもしれない
● でも、子どもはちゃんと成長しているし、親も一緒に成長できる
一番大事なのは、「一人で抱え込まないこと」。
夫婦で話す、医師に相談する、周囲に頼る。
子どもと一緒に前に進むことこそが、親としての大きな役目なんじゃないかと思っています。