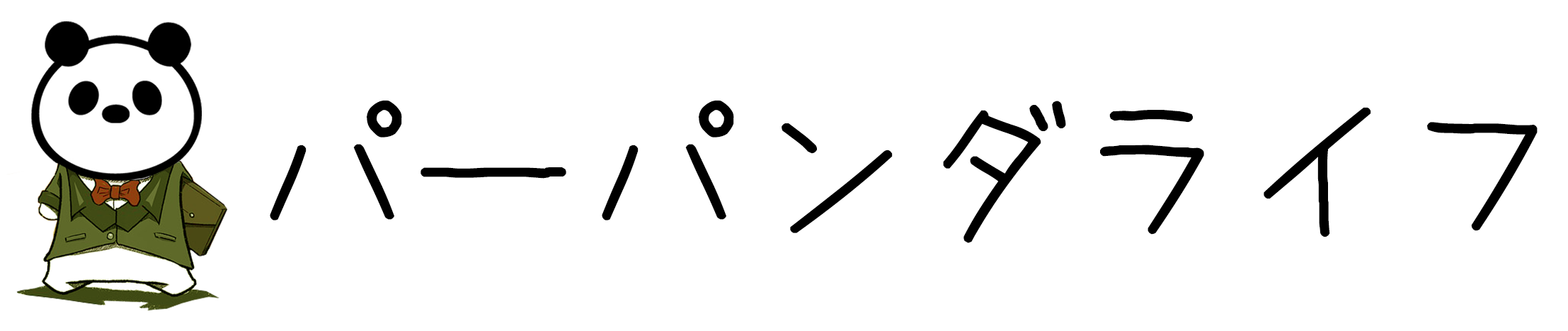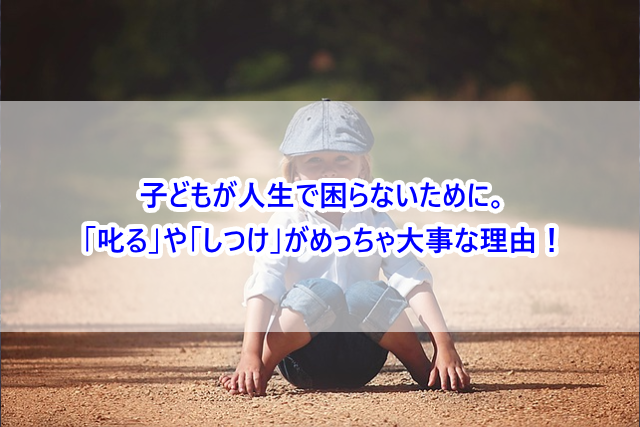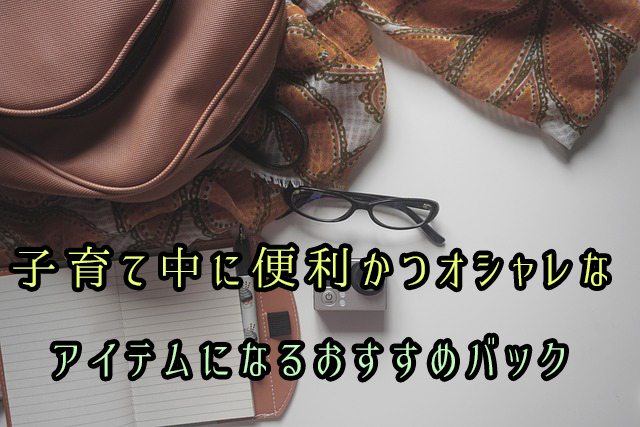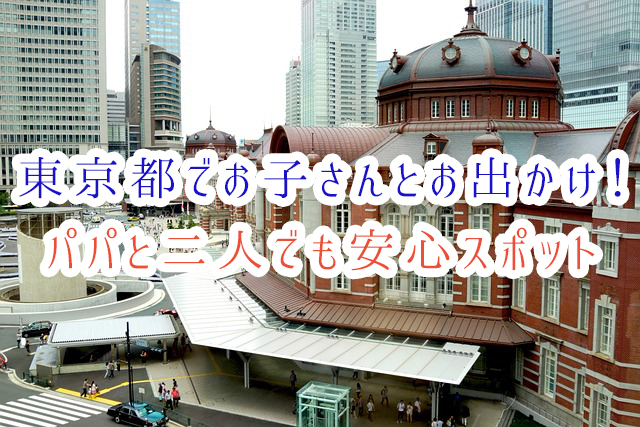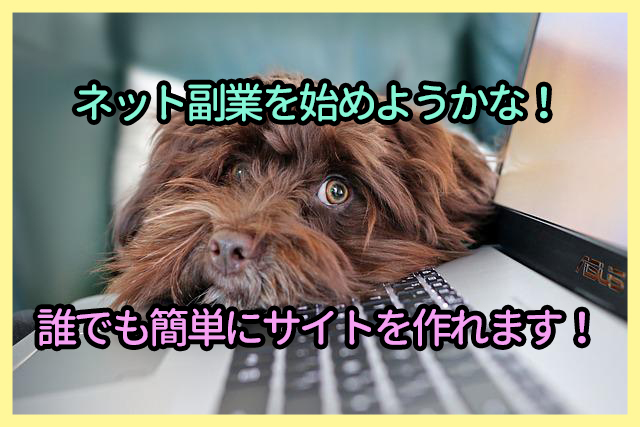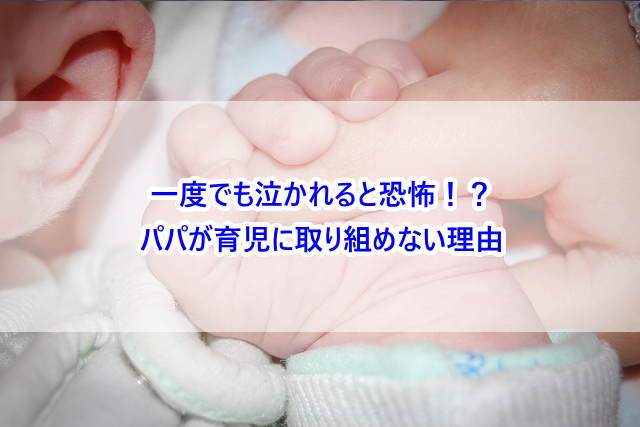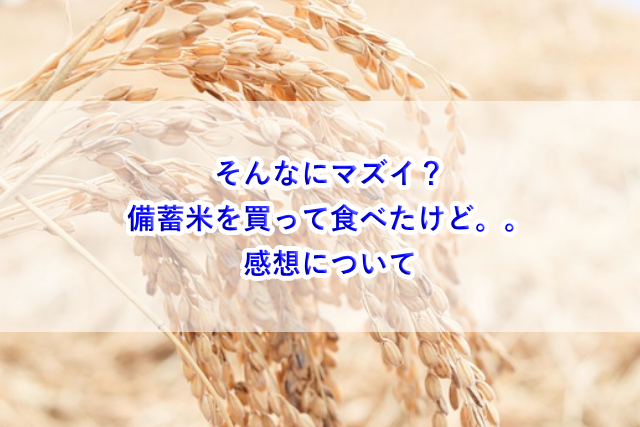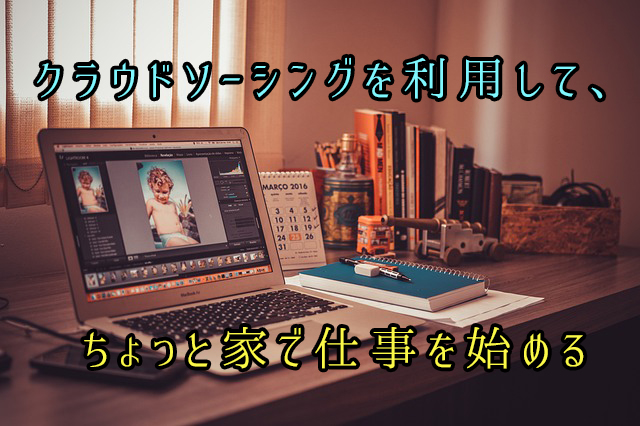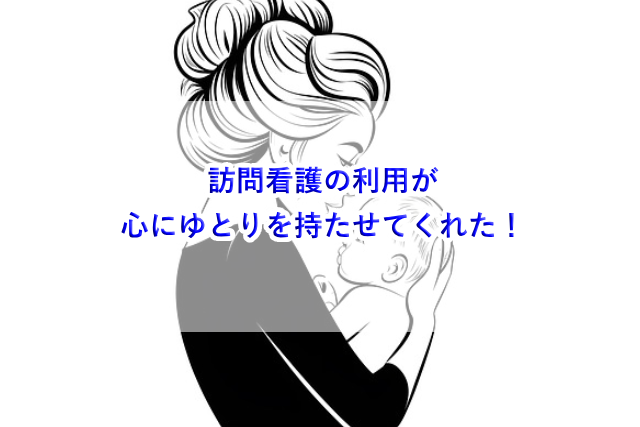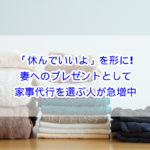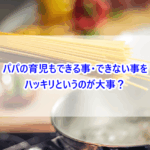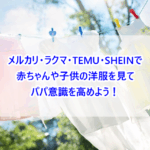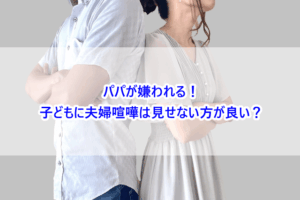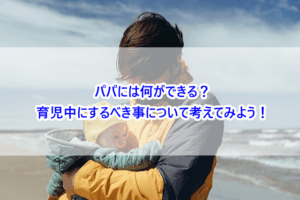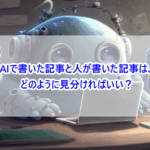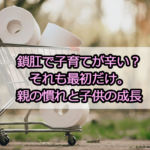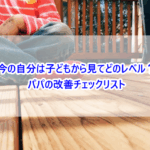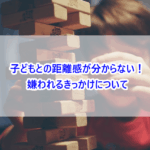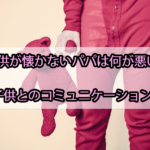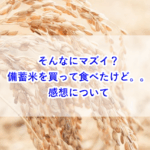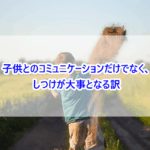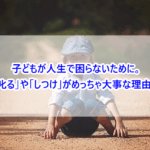「最近、子どもが自分のことを意識的に避けるようになってきた…」
そんな悩みを持つお父さんは少なくありません。特に父と娘の関係では、思春期に距離ができることが多く、「パパ嫌い」という言葉に不安を感じてしまう人もいるでしょう。
でも実際には、必ずしも本当に嫌われているわけではありません。ここでは、なぜそう見えるのか、そして上手に付き合うためのポイントを解説します。
思春期にパパを避けるように見える理由
思春期は子どもにとって大きな変化の時期。心も体も成長する中で、これまでの親子関係が少しずつ変わっていきます。パパを避けるように見える背景には、こんな理由があります。
・心理的な自立の準備
親から離れ、自分の世界を作ろうとする自然な成長の過程です。愛情が薄れたわけではありません。
・異性としての意識が芽生える
父と娘の間では、特にプライバシーを守りたい気持ちが強くなり、距離を取ることがあります。
・コミュニケーションのズレ
年齢や価値観の違いから、会話が噛み合いにくくなることも。興味の対象が違えば話題が減るのも自然な流れです。
こうした変化は一時的なものであり、成長の証でもあります。悲観せずに受け止めることが大切です。
「パパ嫌い」が本当の嫌いではない理由
実は、思春期の「パパ嫌い」には隠れた意味があります。感情の変化や関わり方の違いから距離が生まれますが、それは親子関係の終わりではありません。
・感情の起伏が激しい時期
ホルモンの影響で気分が変わりやすく、態度が急に変わることがありますが、多くは一時的です。
・安心して反抗できる存在
信頼しているからこそ、反発や距離を取る行動ができるのです。
・心の安全基地は失われていない
会話が減っても、心の中では「困ったときはパパが助けてくれる」という安心感を持っています。
つまり、思春期の「パパ嫌い」は、将来の関係を築くための過渡期にすぎません。
思春期の子どもとパパの上手な付き合い方
思春期の子どもとは、距離感と関わり方が重要です。ここでは、父親ができる実践的な接し方を紹介します。
・詮索しすぎない
根掘り葉掘り聞くより、「話したくなったら話してね」というスタンスが信頼を守ります。
・共通の話題を見つける
ゲーム、音楽、スポーツなど、子どもの興味に近いテーマを一緒に楽しむと会話が増えます。
・否定より共感を優先
まずは受け止め、「そういう考えもあるね」と伝えることで安心して話せます。
・距離を尊重する
スキンシップや会話が減っても成長のステップとして受け止めましょう。
・言葉より行動で愛情を示す
送り迎えや静かな見守りなど、態度で示す愛情は長く記憶に残ります。
このように、押しつけではなく「寄り添い」と「見守り」の姿勢が、信頼関係を守るカギとなります。
父と子の関係は回復しやすい
一時的に距離ができても、社会人になったり結婚したりすると、父親の存在が再評価されることは多いです。
「頼れる」「安心できる」という父親像は、大人になってから子どもが改めて感じるもの。
だからこそ、今は無理に近づこうとせず、信頼の土台を守ることが大切です。
まとめ
子どもがなんだか付き合いが悪くなったり、悪態を付くようなことが増えてきたと感じたときは、思春期に突入してしまったのでしょう。
・思春期の「パパ嫌い」は心理的自立や成長のサイン
・無理に距離を縮めず、尊重と共感を意識する
・行動で愛情を示せば、関係は自然に回復する
このような思春期は一時的な親離れの時期ですが、その後の親子関係にとって重要な基礎作りの期間でもあります。
焦らず、長い目で見て子どもとの関係を育てていきましょう。