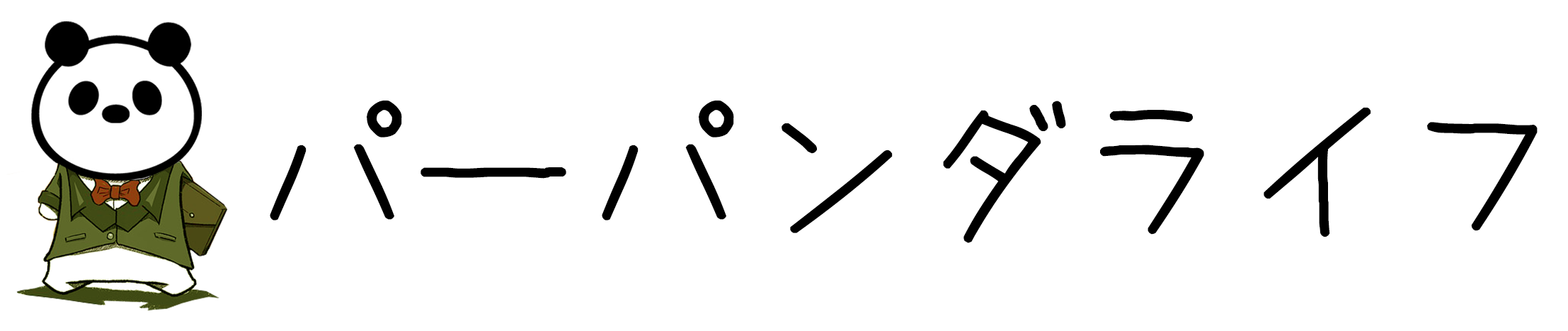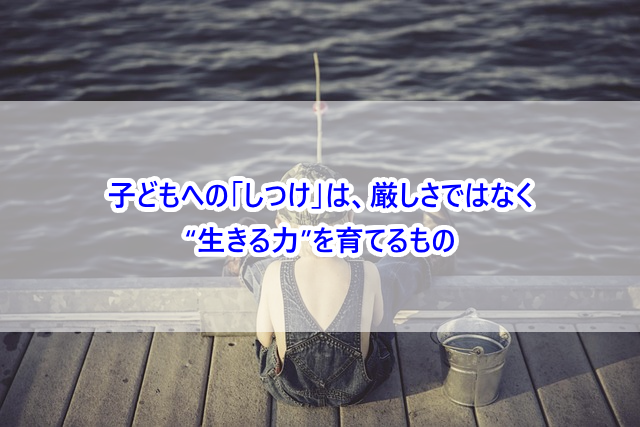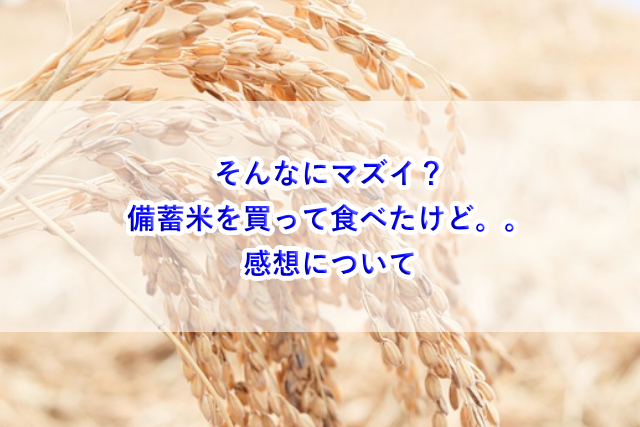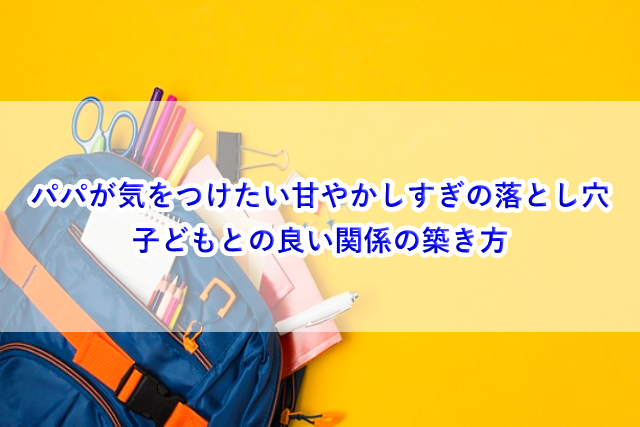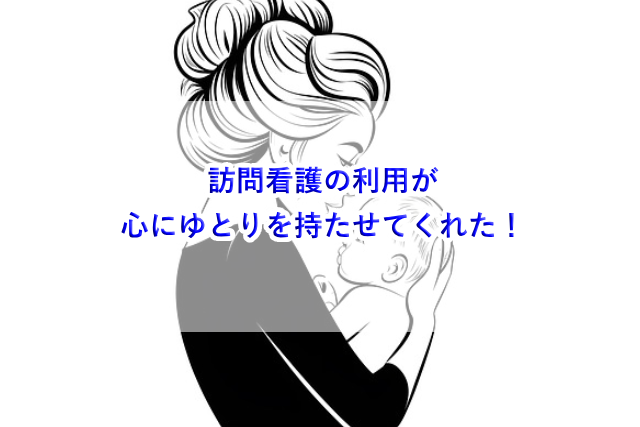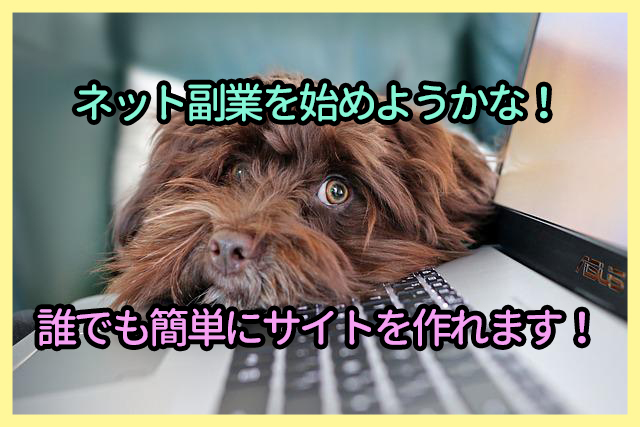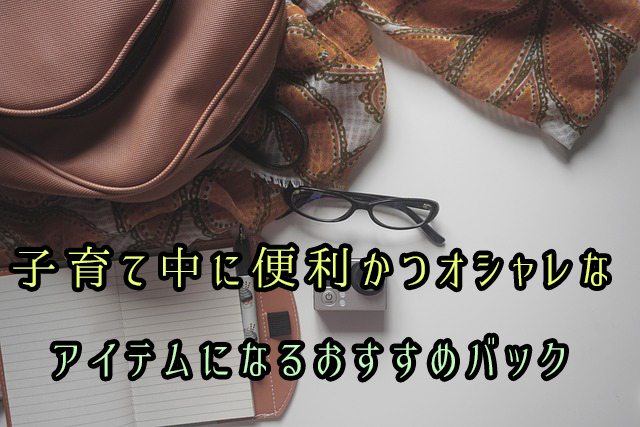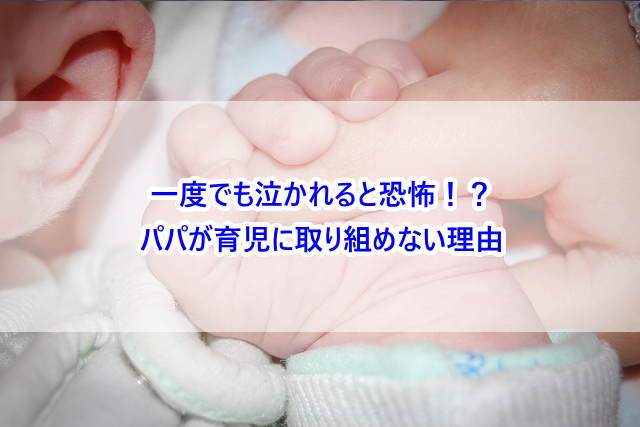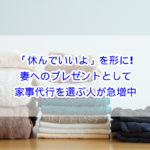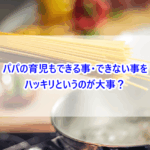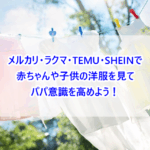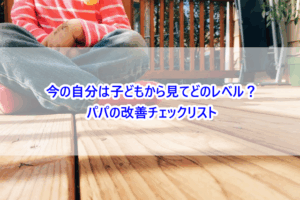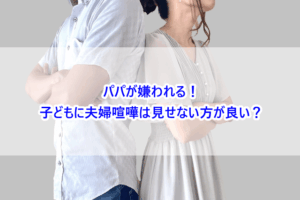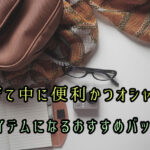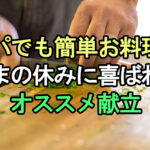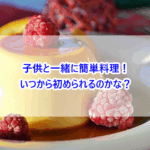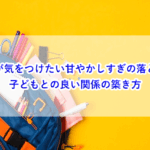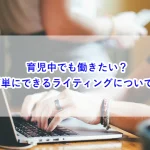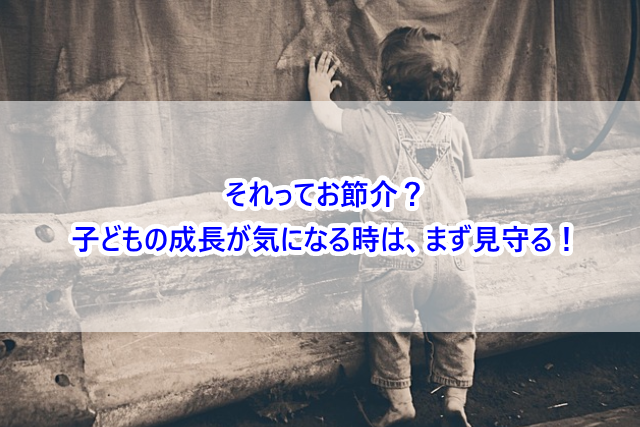
ちょっとお出かけ前だったり、急いでたりすると、子どもの準備にゆっくりと付き合ってられないことってありませんか?
そんな時に、「はやくしなさい!」や無言で靴下や洋服を着替えさせて、お節介してしまうという親御さんは多いかと思います。
今回は、それってお節介?子どもの成長が気になる時は、まず見守る!についてお伝えします。
うちの子は周りよりも成長が遅いかも?
保育園や幼稚園、小学校で他の子どもたちを見たときに、「あれ?うちの子だけまだ○○ができない…」と感じることはありませんか?
靴を履くスピード、服の着替え、片付けの習慣、友達とのコミュニケーションなど、成長のペースは本当に人それぞれです。
しかし、親としてはどうしても「早くできるようになってほしい」「置いていかれないか心配」と焦ってしまうもの。
そんな時についやってしまうのが、子どもの代わりにやってしまう“お節介”です。
お節介が子どもの自立心を奪うことも
親が手伝うこと自体は悪いことではありません。
ですが、毎回のように先回りしてやってしまうと、子どもは「やってもらえるのが当たり前」という感覚になり、自分でやろうとする意欲が薄れてしまいます。
例えば…
靴下を履くのに時間がかかる → 親がすぐ履かせてしまう
スプーンから食事をこぼしてしまう → 親が全部食べさせてしまう
おもちゃの片付けが遅い → 親が全部片付けてしまう
脱いだものをそのまま放置 → 洗濯カゴまで運んでしまう
こうした積み重ねは、本人が「できた!」と感じる機会を減らし、自立心の成長を妨げてしまう可能性があります。
子どもの成長が気になる時は「まず見守る」ことです。
見守るとは?
では、実際に見守るとはどんな性質なのでしょう。
以下の様な行動が「見守る」に該当するとされています。
・手を出さずに、子どもが自分でできるまで待つ
・失敗しても口を出しすぎず、挑戦する時間を与える
・安全面だけ気を配りつつ、本人に任せる
見守ることで、子どもは自分なりに考え、試行錯誤する力を身につけます。
これは学習面や社会性の発達にも直結する大事なスキルです。
見守りのコツ5つ
⓵時間に余裕を持つ
朝の準備など急いでいる時こそ、前倒しで動く習慣をつけましょう。
余裕があれば「早くして!」のプレッシャーを減らせます。
⓶できた部分を褒める
全部できなくても「ここまで自分でできたね!」と肯定的な声かけをすることで、やる気が続きます。
⓷選択肢を与える
「どっちの靴下にする?」と選ばせることで、自分で決める力も育ちます。
⓸お手本を見せる
やり方が分からないときは、一度見せてから「やってみる?」と促すのが効果的です。
⓹完璧を求めない
少し曲がって履いた靴下や、見た目がいびつなお片付けも、「これでOK」と受け止めることが大切です。
成長のスピードは一人ひとり違う
発達心理学でも、子どもの成長には大きな個人差があるとされています。
同じ年齢でも、運動能力が先に伸びる子・言葉の発達が早い子・コミュニケーションが得意な子など、伸びる分野はさまざまです。
親が焦って他の子と比べるよりも、「先月よりちょっとできた」という小さな変化に目を向ける方が、子どもの自己肯定感を育てます。
お節介を減らすと、こんな成長が見られる!
見守る時間を増やすことで、次のような変化にも期待できます。
・自分から行動するようになる
・失敗を恐れず挑戦できる
・親に頼らずできたことに自信を持つ
・他人への思いやりや協力する力が育つ
こうした成長は、学年が上がった時や将来の社会生活でも大きな強みになります。
どうしても心配な時は?
もちろん、「成長の遅れかも?」と感じたら、専門家に相談するのも一つの方法です。
・保育士や担任の先生
・地域の子育て支援センター
・小児科や発達相談窓口
必要に応じて、第三者の視点からアドバイスをもらうことで、安心感を得られます。
もちろん、自身の親御さんに聞いてみるのも良いでしょう。子育ての先輩は案外近くにいますので!
時代は違えど、自分を成長させてくれた先人です。
自分の成長過程を聞いてみると、自分の成長をあまりにも美化している可能性もありますし、なんだ自分も同じだったのかと腑に落ちるケースもあります。
まとめ
子どもの成長は早い時もあれば、ゆっくり進む時もあります。
大切なのは、「できないこと」に注目するのではなく、「できるようになるプロセス」を大事にすること。
お節介を減らし、見守る時間を増やすことで、子どもは自分のペースで確実に成長していきます。
そして、何よりも「パパやママは信じてくれている」という安心感が、挑戦するエネルギーにつながります。
今日から少しずつ、“手を出す前に見守る”を意識してみましょう。
それが、親子の信頼関係と子どもの自立心を同時に育てる第一歩です。