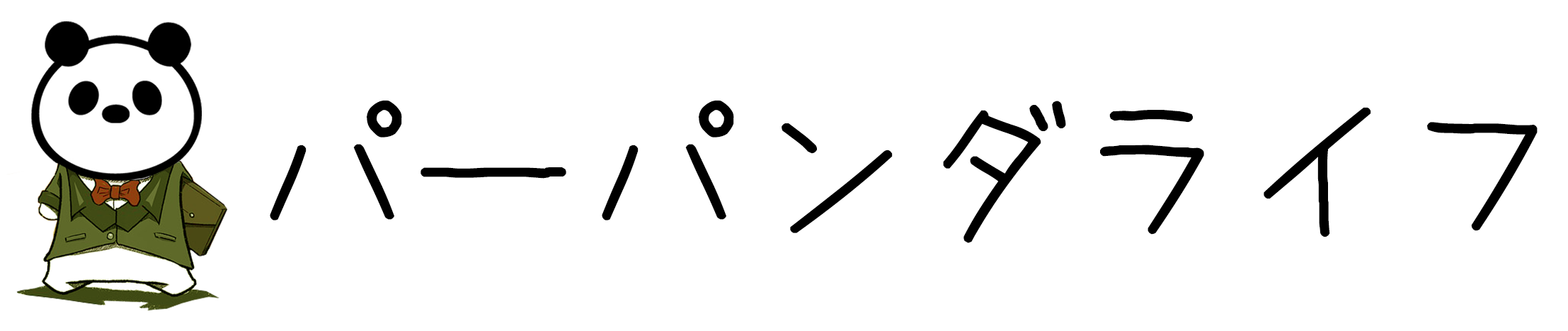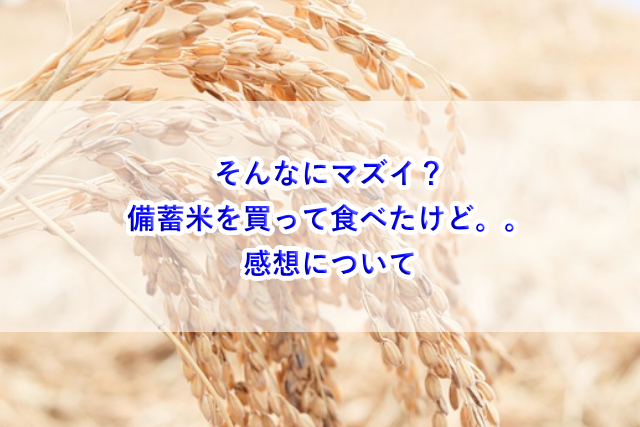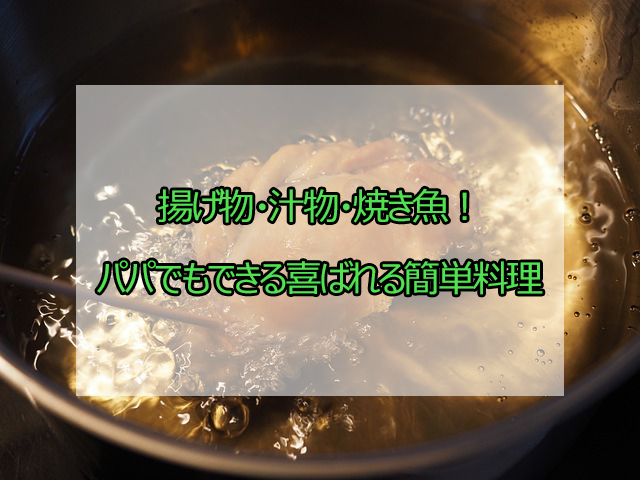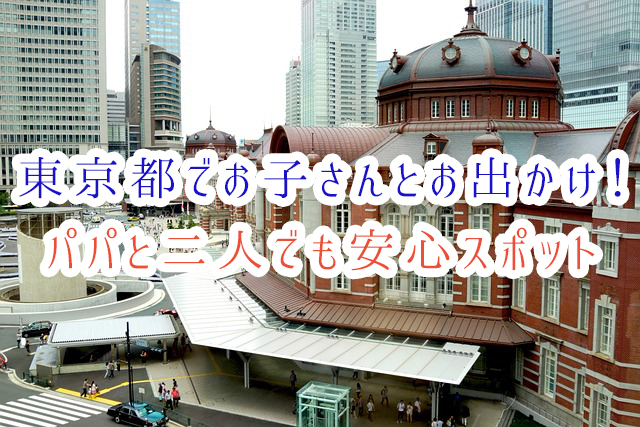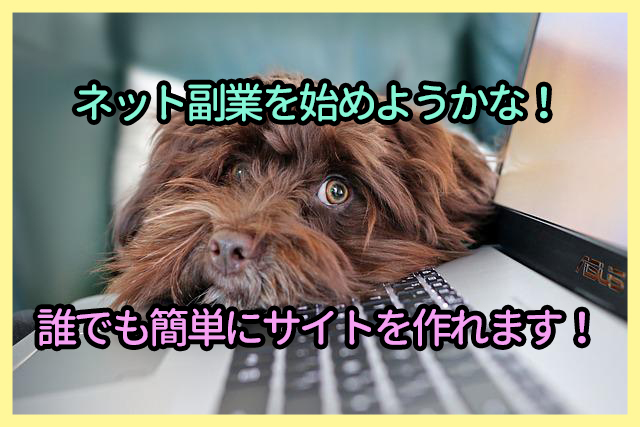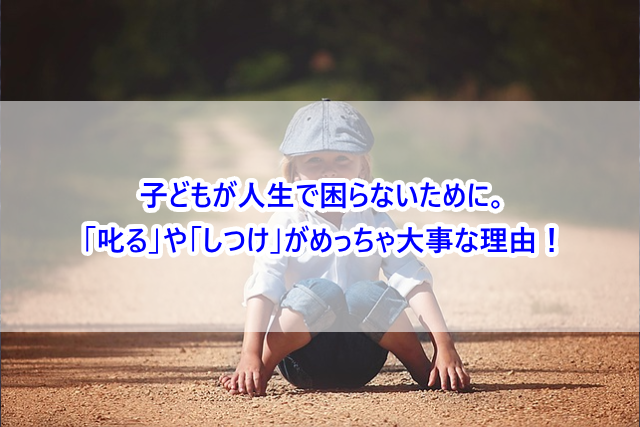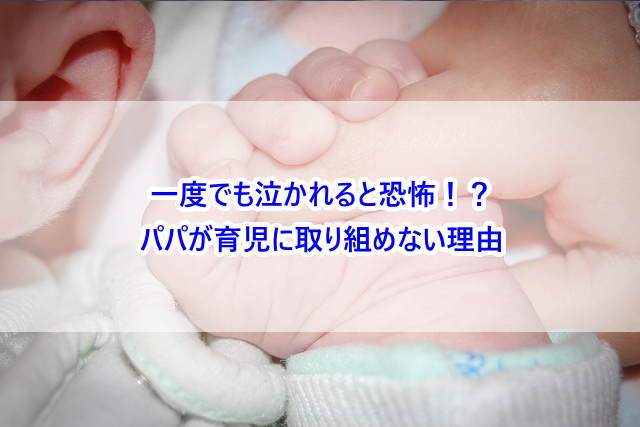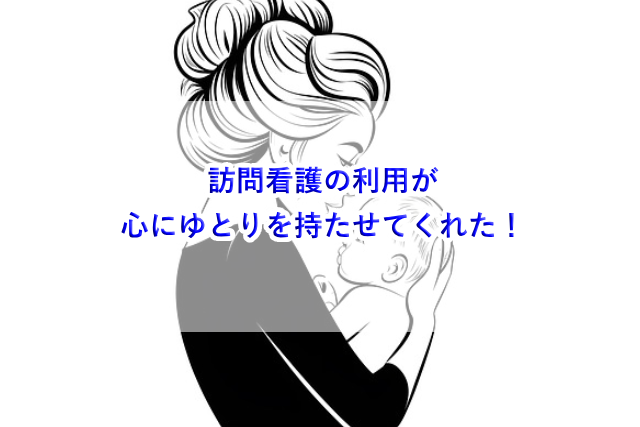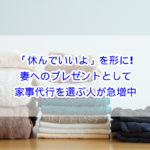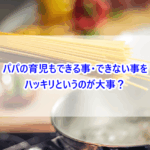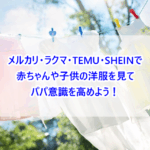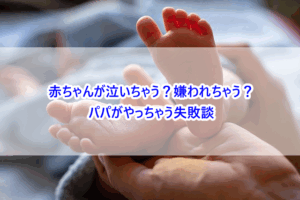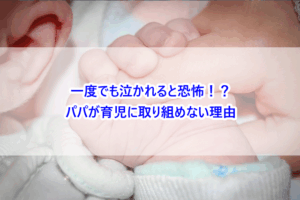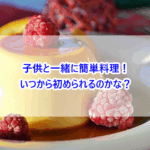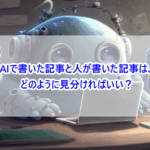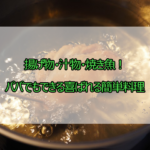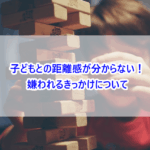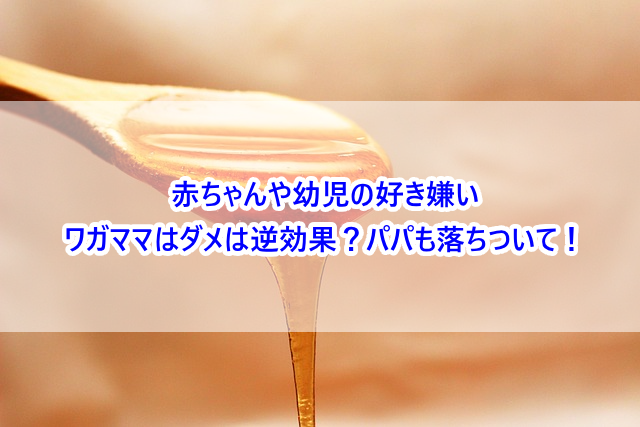
離乳食や幼児食が始まると、パパ・ママを悩ませるのが「食べ物の好き嫌い」です。せっかく作ったのに食べてくれない、昨日まで喜んで食べていたのに今日は口を開けない…。そんな状況が続くと「わがままなんじゃないか?」「しつけが必要なのでは?」と不安になってしまうパパも多いのではないでしょうか。
でも実は、赤ちゃんや幼児期の好き嫌いは“成長の一部”であり、“わがまま”ではありません。むしろ無理やり食べさせようとすると逆効果になりやすく、食事そのものが苦手な時間になってしまう危険もあるんです。
ここでは、子どもの食べ物の好き嫌いについてよくある場面や原因、そしてパパができる上手な対応の仕方を解説していきます。
「好き嫌い=ワガママ」ではない理由
まず押さえておきたいのが、「好き嫌い=ワガママ」と決めつけてはいけないということ。赤ちゃんや幼児の好き嫌いには、次のような理由があります。
舌や味覚がまだ発達途中
大人にとっては“ほんの少しの苦み”でも、子どもには強烈に感じられることがあります。
食感に敏感
柔らかいものは食べるけど硬いものは嫌がる、口の中で繊維が残る食べ物を嫌がる…といったケースも多いです。
見た目や匂いの印象
色が濃い野菜や独特の匂いがする食べ物を本能的に避けてしまうことがあります。
気分や体調の影響
昨日は食べられたのに今日はダメ、というのは珍しくありません。お腹の具合や眠さ、機嫌の良し悪しでも左右されます。
つまり、好き嫌いは「性格」や「わがまま」ではなく、“発達や本能、気分”によるものが多いんです。
パパがやりがちなNG対応
子どもの好き嫌いに直面すると、つい感情的になってしまうパパも多いもの。ですが、次のような対応は逆効果になってしまいます。
1.「残さず食べなさい!」と怒る
叱られて無理やり食べると、子どもは「食事=嫌な時間」と記憶してしまいます。結果としてますます食べなくなり、食卓の雰囲気も悪化します。
2.「好き嫌いばかりしてワガママだ」と責める
子どもにとっては“本当に食べづらい”だけのことなのに、人格を否定されるような言葉をかけられると自信をなくしてしまいます。
3.無理に口へ押し込む
嫌がるのを押さえつけて食べさせると、食べ物に対する嫌悪感が強化されるばかり。安全面でも危険です。
4.食べないとデザートなし!と条件をつける
一時的に効果があるように見えても「ご褒美がないと食べない」習慣を作ってしまい、根本的な解決にはなりません。
好き嫌いへの上手な向き合い方
では、どうすればパパも落ち着いて向き合えるのでしょうか?ポイントをいくつか紹介します。
1.小さな一口から挑戦
「全部食べなきゃ」ではなく、「一口だけ食べてみよう」でOKにするとハードルが下がります。
2.食べられたらしっかり褒める
大人にとっては小さなことでも、子どもにとっては大きな一歩。「食べられたね!」「すごいね!」と笑顔で褒めると達成感につながります。
3.食べやすい形にアレンジ
細かく刻んだり、スープに混ぜたり、可愛い形にしたり。味や見た目を少し工夫するだけで口にしやすくなります。
4.一緒に料理を楽しむ
野菜を洗ってもらう、盛り付けを手伝ってもらうなど、料理に参加すると「自分で作ったから食べたい」という気持ちが芽生えます。
5.無理に食べさせず経験を重ねる
今日ダメでもまた明日。「何度も経験するうちに食べられるようになる」ことは本当に多いです。長期的な目で見てあげましょう。
食卓の雰囲気が何より大切
実は、好き嫌い克服のカギは「食卓の雰囲気」にあります。
「早く食べなさい」「なんで嫌がるの」とプレッシャーを与えるよりも、みんなで楽しく会話をしながら食べるほうが、自然と子どもの食欲は育ちます。
パパが「食事の時間を楽しむ姿勢」を見せることはとても大きな意味があります。笑顔で「おいしいね」と言うだけでも、子どもにとっては安心できる雰囲気になるんです。
まとめ
赤ちゃんや幼児の好き嫌いは、成長過程で誰もが通る道です。決してワガママではなく、体や心がまだ発達途中だからこそ起こる自然なこと。
大切なのは「怒らず」「押し付けず」「楽しく一緒に食べる」こと。
パパが落ち着いて対応できれば、子どもも安心して少しずつ挑戦できるようになります。
「今日は食べられなかったけど、明日は一口いけるかも」
そんな気持ちで長い目で見ていくと、子どもはいつの間にか新しい味に慣れていきます。
育児は失敗やハプニングの連続ですが、食卓を「家族の楽しい時間」として育んでいくことこそ、子どもにとって最高の栄養になるのではないでしょうか。