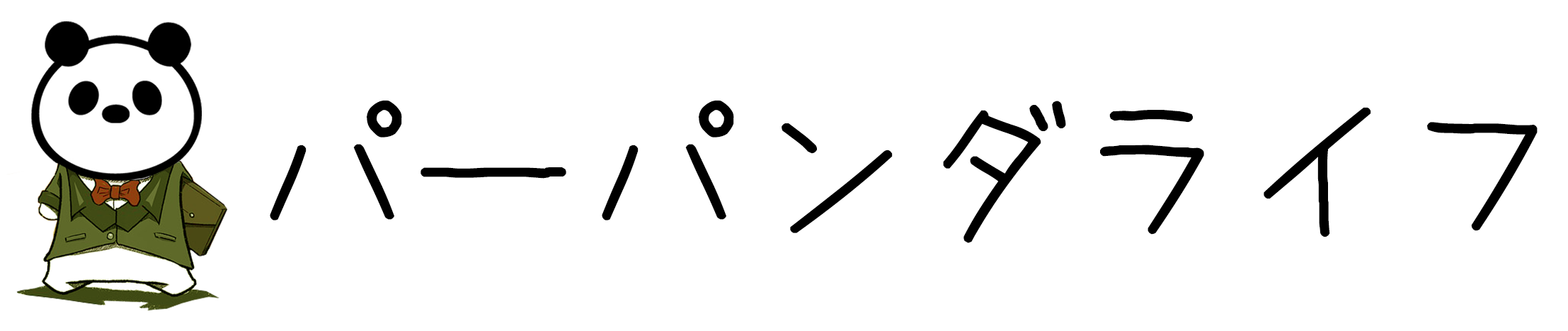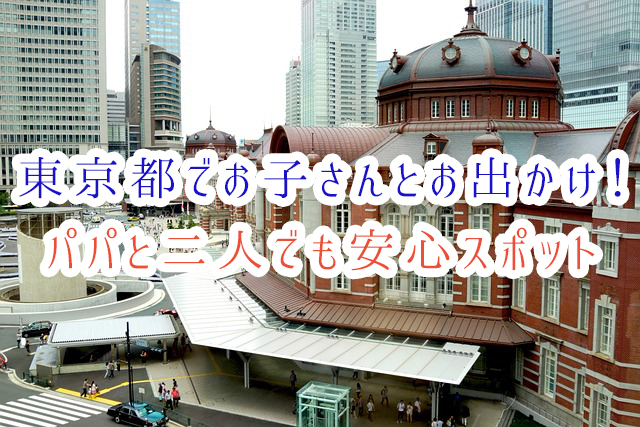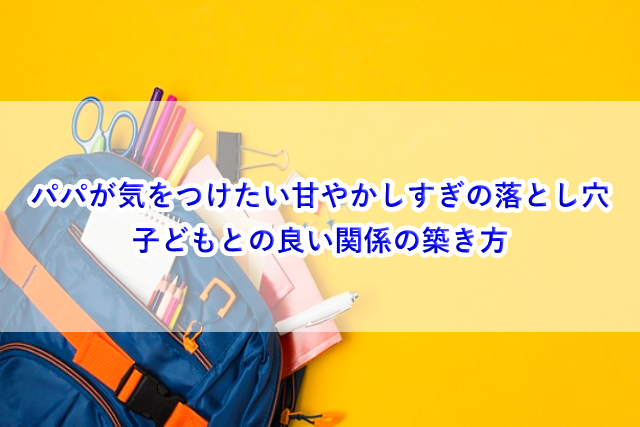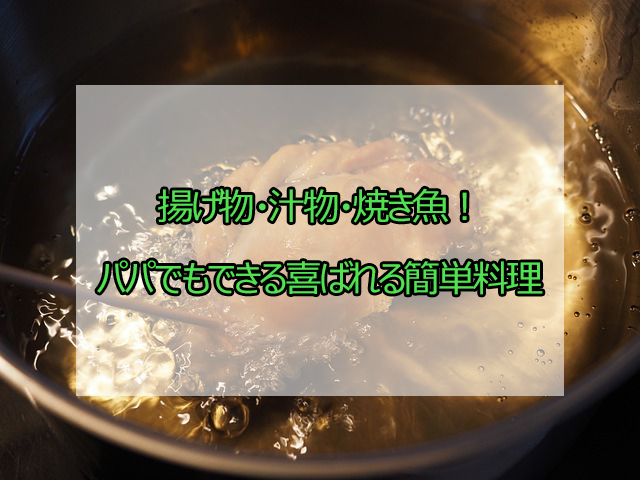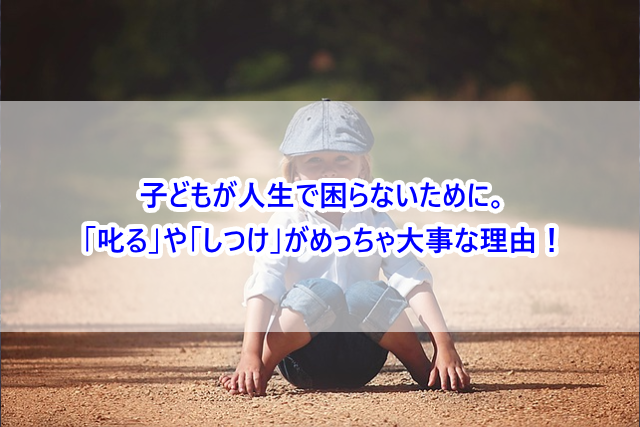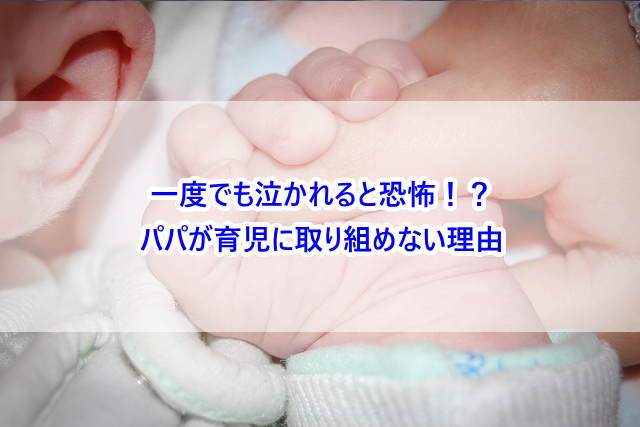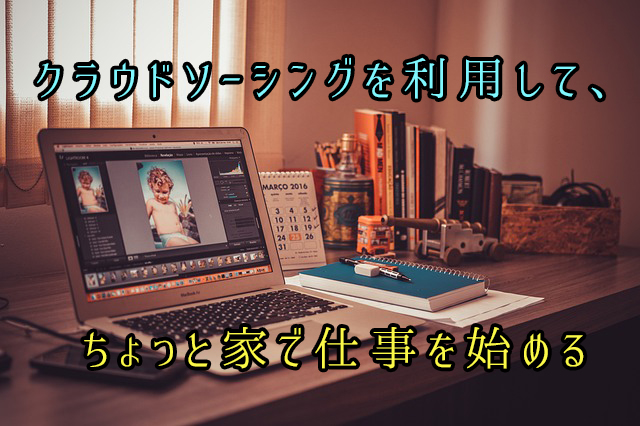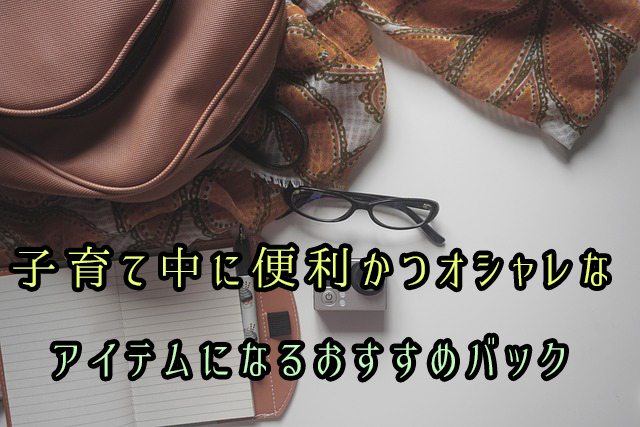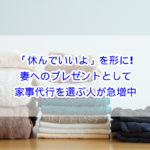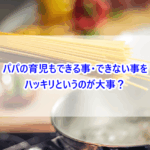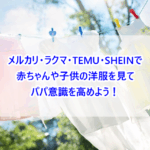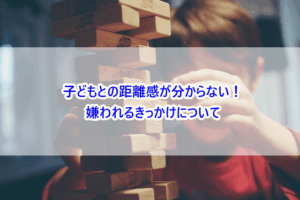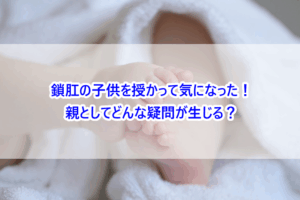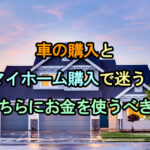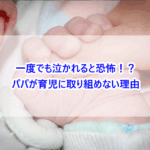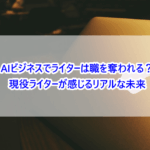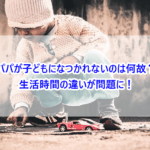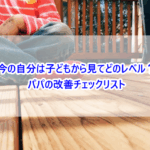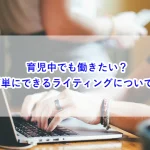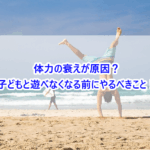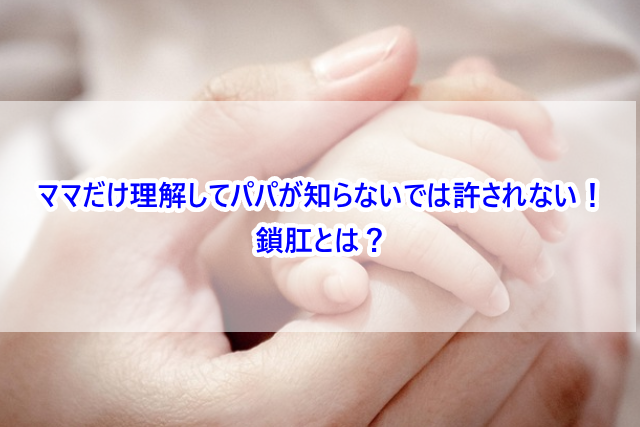
赤ちゃんが生まれた!生を授かって喜んでいるパパも多いと思います。
しかし、その出産に立ち会った後に、お尻の穴が無い。そんなことを言われたパパは、どういう事?と不安になることでしょう。
実際、私がそうでした。ここからは、パパにとって急に我が子が鎖肛と言われた際に、理解しておいた方が良いことについて紹介します。
鎖肛(さこう)ってなに?赤ちゃんに多い病気の一つ
鎖肛(さこう)とは、生まれたときに肛門の穴がふさがっている状態のことをいいます。
赤ちゃんがうんちをするための出口がないため、排便ができず、放っておくとお腹がパンパンになってしまいます。
そのため、産後すぐに手術が必要となるのです。
この時、パパにとって不安な時間が続くことになりますが、医師の話を聞いて、乗り越えるしかありません。
そして、時間が経つにつれ、鎖肛という病気に付いて調べる機会も増えることでしょう。
鎖肛はどうして起こるの?原因は?
赤ちゃんがお母さんのお腹の中で育っているとき、腸や肛門が作られる過程で何らかのトラブルがあり、出口がうまくできなかったと考えられています。
はっきりとした原因は分かっていませんが、鎖肛は遺伝性ではありません。
この病気は、胎児の発育過程で直腸や肛門が正常に形成されない先天性の異常であり、遺伝的な要因は関与していと言われていますので、お母さんが何か悪いことをしたわけではありません!
ですので、ママもパパも、どうか自分たちを責めないでくださいね。
特に、ママは産後鬱などに発展してしまう恐れもあるので、パパはしっかりと、病気について理解を持ち、フォローが非常に大切になります!
どんな症状があるの?
・赤ちゃんに肛門の穴がない、またはとても小さい
・生まれてからうんちが出ない
・お腹がふくらんで苦しそう
尿道や女の子の場合は膣から便が出ることもあります
出産後にこの状態が分かると、病院で検査され、手術などの今後の診断がされます。
どうやって治すの?
治療は手術が必要です。
多くの場合、まずお腹に小さな穴を開けて人工肛門をつくり、便をそこから出せるようにします。
その後、赤ちゃんが大きくなってから、肛門を新しく作る手術を行います。
手術は専門の小児外科医などで行うことになります。
ですので、出産した産婦人科で対応が出来ない場合は、大きな病院への転院が必要となります。
自分のケースは、出産した病院では手術が出来なかったので、出産したその日のうちに運よく大きな病院に転院させてもらえました。
手術可能な病院へ転院した後に、診察などが行われ、手術日程が言い渡されますので、立ち会う様にしましょう。
ママは退院まで日が空くことになるため、パパが主に手術などに立ち会う事になりますし、病状などを聞く事になります。
不安にもなるかと思いますが、医師や看護師さんに分からないことは聞いて、病気に付いて把握していきましょう。
手術したら元気に育つの?
鎖肛という病気を抱えた多くの子どもは、きちんと手術とその後のケアをすれば、普通にご飯を食べて、うんちもできるようになります。
ただし、排便のトレーニングやケアが必要です。
このトレーニングやケアは、生まれて8年たった我が子であっても、まだ完璧に失敗がない状況には成っていません。
もちろん、成長・体つきが大きくなることによって、筋肉量などが増えていき、自身の感覚が養われていけば、問題ない状況になる可能性もあるでしょう。
現在、我が子は、一年に一度、鎖肛の手術を行った病院へ通院し、経過観察している状況です。
まだ、腸などの成長が足りていないため、1週間に一度は浣腸を続けた方が良いと診察されましたので、まだ根治とはなりませんが、うんちを漏らすなどの失敗が減っているのは確かです。
根気強く付き合っていくしかありません。
子どもを怒鳴ってしまったり、自分自身のふがいなさなど、様々な感情が押し寄せてくることもあるでしょう。
ですが、愛情をもって育てると決めたのですから、子ども・ママと一緒に向き合っていきましょう。
では、さらに詳しく説明していきます。
鎖肛の赤ちゃんの育て方
鎖肛(さこう)の赤ちゃんを育てるのは、最初は不安でいっぱいだと思います。
うんちの出口がない、人工肛門がある、手術が必要…聞くだけで大変そうに感じますよね。
でも大丈夫!今は医療も進んでいて、適切な治療とケアをすれば、元気に子供は育ってくれます。
鎖肛の赤ちゃんを育てるうえで大切なポイントをわかりやすくまとめます。
⓵人工肛門(ストーマ)がある時期のケア
鎖肛の手術は一度に終わることが多くありません。多くの場合、まず人工肛門を作って便を出せるようにし、その後に肛門を作る手術をします。
人工肛門がある間は、次のことに気をつけましょう。
・袋(パウチ)の管理
赤ちゃんの皮膚はとてもデリケート。便や袋の粘着部分でかぶれやすいので、皮膚の保護クリームやバリアフィルムを使いましょう。
袋の交換は、便の量や漏れ具合を見て適切に行います。看護師さんから習った方法を守ると安心です。
・皮膚トラブルのチェック
赤くなっていないか、ただれていないかを毎日確認します。
少しでも異常があったら病院に相談しましょう。
⓶手術後の育て方と排便ケア
肛門を作る手術(根治手術)が終わったあとは、排便のトレーニングが必要です。
幼稚園や小学校に上がっても、便が出ているのか分からない・分かっていても言わないなどのトラブル(パンツにうんちがつく)はあるでしょううが、怒鳴ったり・叱っても仕方がないでしょう。
また、その過程で少し漏れているのでは?といった予兆や不自然な行動が見えたら声がけして、漏らす・漏れたことに対して、汚い・不衛生であるということを教えるしかありません。
そして、小学校などに上がればいじめの対象に、なり得ることなどのデメリットも伝えていくしかないのです。
とにかく、本人の意識が変わるまで、気長に付き合うしかありません。
・肛門拡張(ブジー)
手術で作った肛門が狭くならないように、細い器具を使って肛門を広げる練習をします。
最初は怖いかもしれませんが、看護師さんがやり方を教えてくれますので安心してください。
・便のコントロール
はじめは下痢や便秘になりやすいので、食事や水分量を調整しながら様子を見ます。
医師から下剤や整腸剤が出ることもあります。指示を守りましょう。
⓷食事の工夫
離乳食が始まったら、便が柔らかくなりすぎない・固くなりすぎないバランスを意識します。
・水分はしっかりと(便秘防止)
・繊維をとりすぎない(人工肛門がある場合、詰まりやすい食材は注意)
・少しずつ新しい食材を試す
④赤ちゃんとのスキンシップも忘れずに
医療的なケアがあると、「自分の子育ては特別で大変」と感じがちですが、抱っこやお風呂、遊びの時間は他の赤ちゃんと同じように楽しんでOKです。
・泣いたら抱っこして安心させる
・優しく声をかけてあげる
・お風呂は医師の指示に従い、人工肛門の部分を清潔に保つ
⑤ パパ・ママが疲れすぎないために
人工肛門の管理や排便ケアは、最初はとても大変です。
ママだけで抱え込まず、パパも積極的に参加しましょう。
・袋の交換や皮膚のケアは、パパでもできること
・病院での説明は夫婦で一緒に聞くと安心です。
もし、パパが働いていて全て一緒に聞けない場合は、ママにしっかりと確認しましょう。
とにかくママにすべてを押し付けてしまっては、ママの精神も不安定になる恐れがあります。
そうなっては、家庭がボロボロになってしまいますので、しっかりと支えるパパになってください。
かといって、全てを網羅するのも大変でしょうから、不安やストレスは、同じ経験を持つ親のコミュニティや医療スタッフに相談して上手く付き合っていきましょう。
まとめ
病気を持ったお子さんを育てる夫婦こそ、夫婦間での情報共有が非常に大事にもなってきますし、助け合っていかなければなりません。
お互いを思いやる気持ちを大事にして鎖肛を持つお子さんの成長を手助けしていきましょう。
鎖肛についてもっと詳しく知りたいという方は、医師のサイトを参考にして下さい。
あくまで、私の書いたこの記事は、鎖肛を持ったパパが少し知識を付けるための導入的な内容でしかありません。
医学的な用語なども少ないですので、触りについて把握は出来るかと思います。
ですが、お子さんの事を知らないままでは不安となるでしょう。時間がない方は、この記事で少し知識を養ってみてください。